高校を中退したとき、僕の周囲は進学校の制服だらけだった。「俺の人生、もうこれ詰んでないか?」と感じるには十分すぎる環境だったと言える。同級生が大学受験の話をする中、僕には進むべき道が明確に見えず、ただ漠然とした不安だけがそこにあった。コンビニのレジで元クラスメートと遭遇した日には、もうレシートより顔が真っ青になったものだ。彼らは輝かしい未来に向かっていて、自分だけが立ち止まっているような劣等感に苛まれた。
大学に入ってからも、そして就職してからも、僕は常に「他人のルート」と自分を比べていた。SNSを開けば、きらびやかな成功談や、高収入を謳う投稿が目に入る。「彼は一流企業、俺は…どこだ?」「彼女は年収800万、俺は残業代でギリギリ届くか?」。そんな比較の思考が、心の中で無限にスライド再生されていた。まるで自分だけが常に不完全で、何かに追い立てられているような感覚だった。この止まらない「比較地獄」は、僕の心を深く蝕んでいった。
この苦しい状況から、僕はどうやって抜け出したのか。この記事では、僕が実践してきた「他人と比べない生き方」の戦略と、その結果手に入れた「本当の安心」について、これまでの人生を振り返りながら、より深く語っていく。
1. 「比べるだけ」の低コスパ思考からの脱却:自分だけの“勝ち筋”を見つける思考転換
他と比べて落ち込むだけというのは、あまりにコスパが悪い。そう、ある日僕はふと思った。ネガティブな感情に囚われる時間は、何の生産性も生まない。それならば、僕は僕自身の「勝てそうな場所」を選び、そこに全力を注ぐことにしたのだ。
この思考転換は、僕にとって大きなブレークスルーだった。 まず、自分の強みと弱みを徹底的に洗い出した。僕は学校の勉強は苦手だったが、特定の技術分野への興味や、目標達成への集中力は人一倍あった。ならば、その強みを最大限に活かせる場所を探せばいい。
- 勉強が武器になるなら、迷わず資格を取ることを決意した。 専門分野の資格は、学歴のコンプレックスを補い、市場価値を客観的に示す唯一のツールだと考えた。寝る間を惜しんで参考書に向かい、ひたすら知識を詰め込んだ。それは「やらなければならない」という義務感からだけでなく、「これで自分の未来が変わる」という確信があったからだ。
- 環境を選べるなら、福利厚生が強く、安定した会社に行くことを優先した。 一流企業という肩書きよりも、長期的に安心して働ける環境、つまり経済的な安定と精神的な平穏が得られる場所こそが、僕にとっての「勝ち筋」だと見定めた。派手さはなくても、着実に自分の人生を築ける場所だ。
このように、僕は自分で「勝ち筋」を設計し始めた。他人と同じ土俵で戦うのではなく、自分の得意なフィールドで勝負する。この視点を持つことで、社内での評価も、外からの評価も、以前ほど気にならなくなった。「比べてもしょうがない」という諦めではなく、「比べなくても十分にやっていける。なぜなら、自分には独自の勝ち筋があるからだ」という確かな感覚が育っていったのだ。この変化が、僕の「比較地獄」からの脱却の決定的な一歩となった。
2. 他人のSNSから自分のノートへ:視線の転換がもたらす心の平穏と自己成長
SNSは、現代における新たな「比較の温床」だ。他人の「演出された暮らし」がずらりと並び、誰もが最高の一面だけを見せつける。高級ホテルでの滞在、年収1000万の収支公開、海外旅行の連発…。僕も初期の頃は「あ、やべ、全然足りてない」と焦りを感じ、漠然とした不安に駆られたものだ。自分の現状と彼らの「成功」を比較し、劣等感に押しつぶされそうになったことは一度や二度ではない。
でもある日、ふと「note」を書いてみた。それは誰に見せるためでもなく、自分の考えを整理するためだった。日々の出来事、感じたこと、学んだこと、そして自分の理想と現実。それらを文字にしてアウトプットする作業は、想像以上に心を落ち着かせた。自分の思考が明確になり、混乱していた頭の中が整理されていく。
この時、僕は大きな変化に気づいた。それまで「他人に向けていた視線」が、自然と「自分に向かう視線」へと変わっていたのだ。他人の投稿を見て「自分には何が足りないのか」と探すのではなく、自分のノートやブログに書かれた内容を見て「自分は何を考え、どう行動すべきか」と内省するようになった。
ブログも始めた。読まれることもあれば、そうでないこともある。それでも、自分の「納得」が積み上がっていく感覚が心地よかった。誰かの評価を気にするよりも、自分の内面と向き合い、アウトプットする行為の方が、はるかに精神的な安定と自己成長をもたらすことを知ったのだ。SNSでの「演出された成功」を眺めて消耗するよりも、自分の「確かな足跡」を築き上げる喜びの方が、はるかに大きかった。

3. 他人は他人、僕は僕──「地味でも心地よい」今の生き方が僕の勝ち方
現在、僕の金融資産は約4000万円になった。これは、一握りの富裕層から見れば大した額ではないかもしれない。しかし、僕は高卒認定から大学へ進み、パワハラを経験し、一度は退職を余儀なくされた人間だ。そう考えると、この数字は、僕にとっては大きな努力と工夫の結晶であり、揺るぎない自信に繋がっている。
地元の大手企業に転職し、地方の3LDKの社宅に月家賃2.7万円で住んでいる。通勤時間は短く、家族との時間も十分に取れる。妻はブランド品に全く興味がなく、外食はスシローで十分に満足するタイプだ。贅沢を言えばキリがないが、僕たちの暮らしは質素ながらも、精神的な豊かさに満たされている。
たぶん、都心でバリバリ働いている人や、SNSで豪勢なライフスタイルを見せつけるインフルエンサーから見れば、「なんか地味だな」と思われるかもしれない。SNS映えもしないだろう。しかし、僕にとってはこの地味な生活こそが、「ちょうどいい、僕だけの勝ち方」なのだ。
他人の基準ではなく、自分自身の「心地よさ」と「安心感」を追求する。この明確な軸があることで、見栄や無駄な出費から解放され、心穏やかな日々を送ることができている。これが、僕が探し求めていた本当の豊かさであり、比較地獄から抜け出した先に見つけた景色だ。
おわりに:自分軸を持つと、世界は驚くほど静かになる
他人の評価や基準から自由になることは、想像以上に静かで、清々しいものだ。まるで耳鳴りが止んだかのように、心の中の雑音が消え去る。耳元で誰かが「それでいいのか?」と囁いてくることもない。
この「静けさ」の中で、僕は自分自身と深く向き合うことができるようになった。「自分が何を大事にして、何を選ばないか」を深く考える時間が持てるようになり、ひたすら「自分を整える」ことに集中できるようになったのだ。それは、僕が「頑張らないための努力」で築き上げてきた「仕組み」とも深く連動している。
そして、こうして静かに、しかし着実に築き上げてきた日々の中にこそ、「本当の意味での安心」が確かに眠っている気がする。それは、外部の評価に左右されない、内面から湧き上がる確かな自信と平静さだ。
だから今日も、僕は誰とも比べず、淡々と、心地よく生きていく。

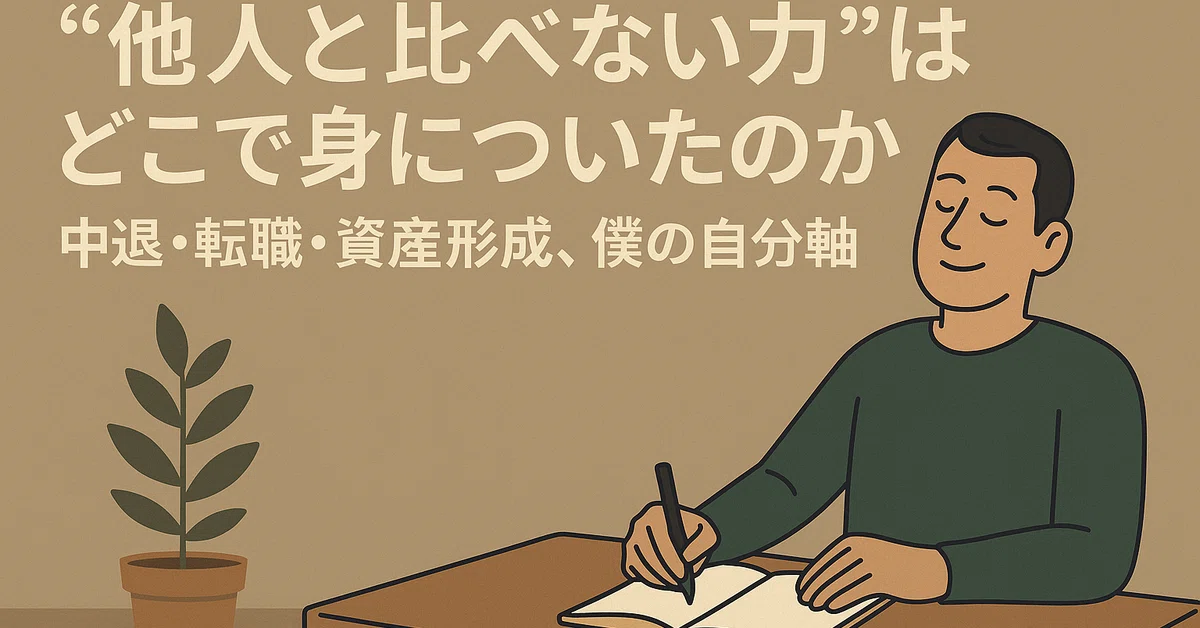


コメント