昔はあったんです、“ゾーンに入る”瞬間。
気づけば4時間ぶっ通しで勉強してた。
アイデアが止まらなくて夜中にメモがびっしり。
深夜テンションで課題を仕上げ、翌朝それなりの評価。
──でも、あれ、もう無理じゃない?
いまや10分スマホを見ただけで、
「あれ、何しようとしてたっけ?」と立ち尽くす日々。
そう、集中力はもう戻らない。
……いや、もっと正確に言うなら「集中しない前提で動くしかない」のだ。
集中力は“劣化”じゃない、“有限資源”だった説
若い頃、「集中力が落ちたな」と思うことはなかった。
でも30代を超えると、明らかに“ムリが効かない”。
理由は単純。
脳も体も、限られたエネルギーをどう使うかという問題に直面するから。
科学的にも、集中力って“バッテリー式”なんですよね。
- 朝はフル充電
- 昼食後に50%
- 午後3時は残り10%
- 夜は「もう勘弁してくれ」
しかも、このバッテリー、通知やタスクの切り替えでめっちゃ減る。
- Slackが鳴ったら−15%
- LINEがピコンで−10%
- ブラウザのタブが10個開いて−30%
そりゃ1日もたない。
昔の僕:「集中できないのは根性不足だ」と思ってた
当時の僕は、「集中できない=甘え」だと思ってた。
・コーヒーをがぶ飲みして目を覚まし
・気合いでタスクを完遂し
・「今日は全然休めなかったな〜(ドヤ)」と寝落ちしてた
結果、どうなったかというと、燃え尽きる。
メンタルも体調もガタガタ。
好きだったはずの仕事や勉強が、「やらなきゃならない義務」 に変わった瞬間だった。
僕が実践している“集中しない戦略”
いまの僕は、集中力に期待しない。
それよりも、“集中できなくても進む仕組み”を組むようにしている。
1. やらないことを決める
まず、削る。
- 朝のSNSチェック禁止
- 通知はオフ
- マルチタスクはしない
「やること」より「やらないこと」 のほうが、脳の省エネにつながる。
2. 毎朝やることは“半自動化”する
朝のルーティンを決めておくと、脳がスリープ状態でも動ける。
- 起きたら白湯
- 机に座ったらNotionを開く
- スマホは別部屋へ
- 1タスク目は“考えなくて済む作業”にする
もはや、「考えないこと」が正義。
3. タスクは“分解”しておく
「ブログを書く」だと脳がビビる。
だから、こうする:
- 見出しだけ書く
- 導入だけ書く
- 100文字だけ書く
階段を1段ずつにするだけで、着手ハードルが激下がり。
4. 集中できる“時間帯”を使い倒す
僕の場合、朝〜午前10時くらいが唯一のゴールデンタイム。
午後は仕事をしているフリが得意な時間帯なので、なるべく軽めの作業。
夜はもう…「なんか今日も終わったな〜」の感傷タイム。
つまり、
集中できる時間=貴重な資産
としてスケジューリングするのが肝。
5. 集中せずに動くための“補助輪”をつけておく
- タイマーで25分ポモドーロ法
- やることをノートに手書きで可視化
- PCのデスクトップはスッキリ
- 迷ったら「書きながら考える」にする
これらはすべて、“集中しない脳”でも前に進むための工夫。
「全集中」より「全自動」の方がラク
昔は「今日はめっちゃ集中できた!」という日がたまにあった。
でも、いまはもう違う。
- 集中できなくても、進む設計にする
- 判断しなくても済むように、事前に分解する
- 気分が乗らなくても、やれる「最低限」のラインを作っておく
僕の集中力はもはや“気分”ではなく、“仕組み”で支えられている。
結論:集中力は才能じゃない、“整った環境”の副産物
集中力の高い人って、別に「特別な人」じゃない。
ただ、
- 静かな場所で
- ちゃんと寝て
- やることが明確で
- スマホが遠くて
- 決断疲れしてなくて
という条件がそろってるだけだったりする。
つまり、“集中力”は出すものじゃなく、“出る状態にするもの”。
今日も「集中せずに」前に進もう
僕はもう、若い頃のように“ノってくるまで粘る”みたいなことはしない。
ノってこなければ、
ノらなくてもできる仕組みにしておく。
それが、
大人のための“集中しない戦略” だと思ってます。
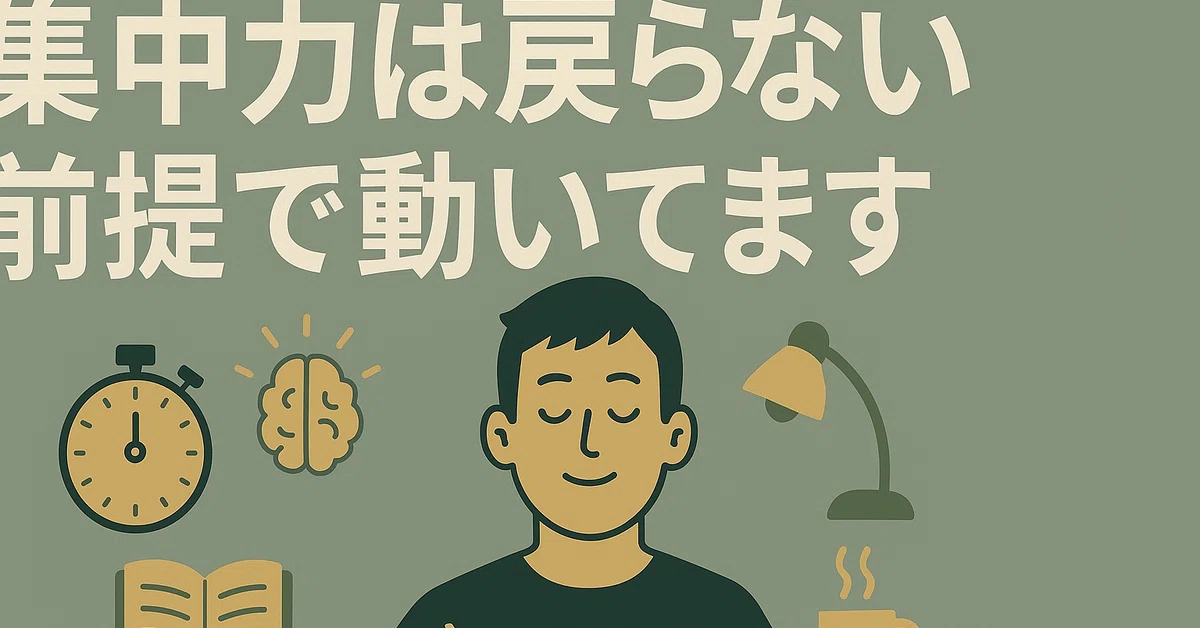
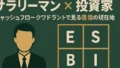

コメント