転職して、早くも一年が経ちました。そして今、私は育児休業を取得し、会社という組織から少しだけ距離を置いています。「距離を置くと見えてくるものがある」とはよく言われることですが、本当にその通りだと実感しています。会社という存在は、あまりにも近すぎると、まるで空気のようにその存在を意識しなくなるのだと。
この育休期間を通じて、今の自分にとって「サラリーマン」という働き方がどのように映っているのか、じっくりと考える時間を得ました。その結果、たどり着いたのは、思いのほか「気楽」で、それでいて「でも別に大きく変えたいとも思っていない」という、なんとも中途半端ながらも、私にとっては非常にしっくりくる「中庸」の境地でした。今日は、この「サラリーマン」という働き方から見えてきた、私なりの発見と価値観についてお話ししたいと思います。
「守られる」って、実はすごくありがたい──サラリーマンという「人間へのやさしい仕組み」
育休に入って改めて感じたのは、サラリーマンというシステムが、いかに「人間にとってやさしい仕組み」であるかということです。
- 明確な時間軸: 毎日決まった定時があり、それに合わせて働くことができる。
- 安定した収入: 毎月決まった日に給料が振り込まれる安心感。
- 手厚い保障: 誰かが決めてくれたスケジュールに沿って働くだけで、社会的信用はもちろんのこと、年金や健康保険といったセーフティネットまでが自動的に付いてくる。
これらは、個人事業主やフリーランスとして働くことを考えれば、どれも自分で手配し、管理しなければならない重い責任です。サラリーマンは、まるで「やさしさの押し売りじゃないか?」と思うくらいの充実っぷりだと、今なら素直に感じます。
特に、転職後は人間関係のギスギスが大幅に減り、「あれ、意外と快適かもしれない」と思えるようになりました。以前の職場では、人間関係のストレスが大きく、それが「会社を辞めたい」という気持ちに繋がることも少なくありませんでした。しかし、今の職場では、業務に集中できる環境が整い、精神的な負担が軽減されたことで、サラリーマンであることのメリットをより強く感じられるようになったのです。
「こうして、人はぬるま湯に浸かっていくのだな……」と、どこか自嘲気味に笑いながらも、その「ぬるま湯」の温度が、今の自分にとってちょうど良い季節が人生にあってもいいじゃないか、と心から思うようになりました。無理に熱い風呂に入る必要はない。心地よい温度で、ゆったりと過ごす時間もまた、人生の豊かさの一部なのです。

「自由ではない」けど、今はそれが「ありがたい」という感覚
もちろん、サラリーマンである以上、“完全に自由”というわけではありません。会社が決めた目標をこなし、時にはその意味がよく分からない資料をまとめたり、年に何度か上司と向き合って「これが評価か……」と心を無にしたりする瞬間もあります。
しかし、不思議なことに、それでも「辞めたい」とまでは思わないのです。むしろ、「この会社に、もう少しの間、いさせてもらえたらありがたいな」くらいの、穏やかな気持ちが湧いてきます。
かつては「いつか独立するぞ」「もっと自由な働き方を」といった「攻め」の姿勢でキャリアを考えていた時期もありました。しかし今は、どちらかといえば「攻め」よりも「しがみつきたい」という気持ちの方が強い。あえて険しい崖を登って新たな景色を見るよりも、今いる場所から滑り落ちないように、足元をしっかりと固めていたい。そんな堅実な考え方が、今の私にはしっくりきています。これは、決して向上心がなくなったわけではなく、人生における優先順位が変化した結果だと感じています。

育休で見えた「会社とのちょうどいい距離感」
育休中の日々は、まるで時間がスローモーションのように流れていきました。朝は子どもの機嫌と、その日の天気によってスケジュールが左右され、昼間は「この公園の滑り台、静電気がすごいな…」など、普段の会社生活では気づかないような、妙な観察力ばかりが鋭くなる。
そんな穏やかな時間の合間に、ふと仕事のことを思い出すことがあります。「あ、今ごろ○○さんは進捗管理表をいじってるかな」とか、「あのプロジェクト、どうなったんだろう」とか。
でも、それが恋しくてたまらないわけでも、あるいは二度と会社に戻りたくないわけでもありません。ただただ、「あの世界も、自分の一部だったなあ」と、遠い昔を懐かしむような、穏やかな感覚があるだけです。
この育休という期間が、会社との距離をうまく**“ほどいて”**くれたのかもしれません。以前のようにべったりと会社に依存する必要はないけれど、完全に縁を切りたいわけでもない。そんな「ちょうどいい距離感」が、今の私には何よりも心地よくなってきたのです。これは、精神的な自立と、組織への適度な帰属意識のバランスを見つけた、ということなのかもしれません。

サラリーマンという生き方は、「中庸」でいい
昔の私は、「いつか独立して自分のビジネスを立ち上げるぞ」とか、「もっと自由な働き方を追求したい」といった、ある種の理想像を追い求めていました。しかし、最近は、「このままでも、わりと悪くないぞ」という気持ちの方が、圧倒的に強いです。
もちろん、将来への備えは、これまで通り着実に続けています。資産形成のための投資、スキルアップのための副業、そしてキャリアの棚卸しとしての資格取得。これらは、私の人生の基盤を固めるための重要な活動です。
ただ、それらの備えは、「万が一の時に独立するため」というよりも、「備えがあれば、もう少し“気楽に流されて”もいいかな」という、心の余裕と安心感を得るための前提づくりへと変化しました。
サラリーマンという生き方は、確かに「自由」ではありません。しかし、その一方で、すべてが「不自由」というわけでもない。会社という大きなシステムの中に身を置きながら、少しずつ自分の時間に重心を移していく──それは案外、華々しいFIRE(経済的自立と早期リタイア)を目指すよりも、「穏やかで、持続可能な選択」なのかもしれないと、今ではそう感じています。
最後に──「動かなくてもいい」という安心感
「今は動きたくないわけじゃない。でも、無理に動かなくてもいいかな」──そう思える状態にあること。これこそが、実は今の私にとって、何よりも大きな安心材料なのかもしれません。
私は今、会社という巨大なシステムに、まるでそっと寄り添うように「しがみついて」います。そして、その足元で、自分の暮らしや人生を、焦らず、しかし着実に耕している最中です。この「中庸」の生き方が、私にとっての新しい幸福の形なのかもしれません。
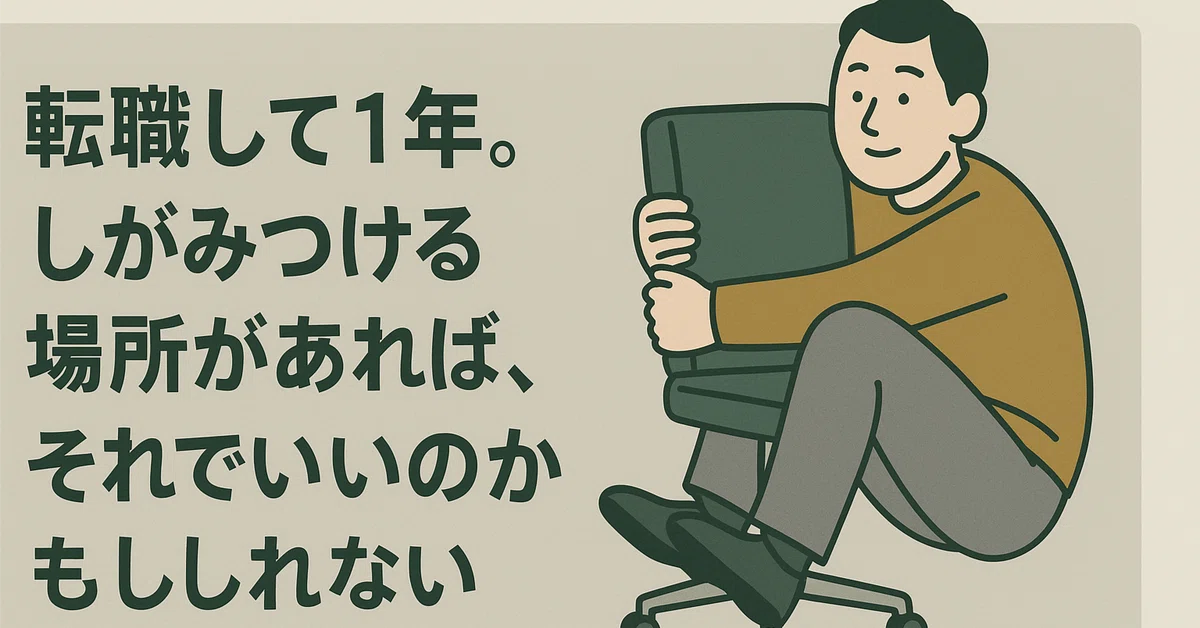

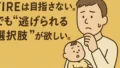
コメント