プロローグ:あの日、僕はレールを外れた
高校を中退する、という決断を下したあの日、僕は一般的な「レール」から大きく外れました。周りの友人が当たり前のように高校生活を送り、大学進学を目指す中で、僕の未来は真っ白なキャンバス、いや、むしろ霧に包まれた荒野のようでした。世間一般から見れば、それは「失敗」であり「ハンディキャップ」。常に漠然とした不安と、人とは違う道を歩むことへの焦燥感が、僕の心の中に横たわっていました。
しかし、この「レールからの離脱」が、僕の人生において、結果的に最大の転機となったのです。それは、社会的な「守り」がないからこそ、自分自身の力で人生を切り開くという、根源的なサバイバル意識が芽生えた瞬間でした。そして、その意識は、後の僕の「資産形成」と「働き方」の哲学へと深く繋がっていくことになります。
第一章:漠然とした不安が僕を「自己投資」へ駆り立てた
高校中退という経験は、僕に強烈な危機感を与えました。学歴という社会的な武器を持たない僕が、どうすれば社会で自分の居場所を見つけ、生きていくことができるのか。この漠然とした不安が、僕を「自己投資」という道へと強く駆り立てました。
学歴がないからこそ、知識とスキルを渇望した日々
僕にとっての最初の自己投資は、高校中退からの大学受験という、ある種の「逆転劇」でした。一般的な受験生とは異なるスタートラインに立ち、独学で必死に学んだ経験は、僕に「やればできる」という小さな成功体験と、知識を身につけることの楽しさを教えてくれました。勉強自体を「スポーツ」のように楽しめたのは、その後の人生においても大きな財産となりました。この経験は、まさに「自己責任」という名のエンジンを僕の人生に搭載するきっかけでもありました。
社会人になってからも、この「知識を渇望する」姿勢は変わりませんでした。会社という組織の中で自分の存在意義を確立するため、僕は「資格取得」に猛烈な勢いで取り組みました。ネットワークの部署から始まり、サーバー、クラウド、セキュリティと、異動のたびにその分野で必要とされる資格を最短で取得することを目標に掲げたのです。
「実務経験を積んでから資格を」というセオリーとは真逆で、僕は専門用語の意味もよくわからないまま、ひたすら暗記し、資格を取ることに全力を注ぎました。それは、「とにかく資格を取って、ここにいていい理由をつくる」という、僕にとっての第一ミッションだったからです。過去のパワハラ経験も相まって、「自分の居場所」が社内で明確になるまでは、毎日が綱渡りのような精神状態でした。資格という具体的な「紙の証明書」は、そんな僕のメンタルを安定させるための、何よりも重要な土台でした。詳しい経緯は「資格で掴んだ「僕だけの居場所」:苦手な会社で生き残るための、地道で確実なサバイバル戦略」で語っています。
気がつけば、社会人15年目で取得した資格は20個以上。AWS SAP、CISSP、PMPといった高難度な資格から、TOEICのスコア向上まで、地道な努力を積み重ねてきました。これらの資格は、僕の「人的資本」を飛躍的に高め、会社内での専門性に対する信頼を静かに、しかし確実に築いてくれました。


第二章:「守り」としての資産形成:お金が僕にもたらした心の余裕
資格取得を通じて「人的資本」を積み上げる一方で、僕がもう一つ並行して取り組んできたのが「金融資本」、すなわち「資産形成」です。高校中退という経験から得た「社会的なセーフティネットがない」という感覚は、経済的な「備え」の重要性を僕に強く意識させました。
「学歴」という無形資産がない分、「お金」という具体的な保険を
学歴という一般的な「無形資産」がないと感じていた僕は、それを補うかのように、目に見える「お金」という具体的な保険の必要性を感じていました。それは、万が一の事態に備えるだけでなく、人生の選択肢を増やし、精神的な自由を手に入れるための手段でした。
当初、資産形成は純粋に「お金を増やすこと」が目的でした。しかし、育児休業に入り、赤ちゃんとの日々を過ごす中で、その目的は大きく変化しました。今は、「働くことへの心理的な“圧”を減らすこと」が最大の目的になったのです。
- 会社での仕事に全身全霊を捧げなくても、家族と生活していけるだけの基盤を築きたい。
- 理不尽な状況に直面しても、それに我慢し続ける必要はなく、いつでも別の選択肢を選べる状態にしておきたい。
これこそが、現在の僕にとっての真の「資産形成」なのです。資産を増やすことは、あくまでこの「圧を減らす」という目的を達成するための手段であり、それ自体がゴールではなくなりました。
第三章:育休中に見つけた「窓際FIRE」という新境地
育児休業という期間は、僕に会社という存在と自分の働き方を客観的に見つめ直す機会を与えてくれました。会社から物理的に距離を置くことで、見えてきたのは、サラリーマンという働き方が持つ「人間へのやさしい仕組み」でした。定時があり、決まった給料があり、年金や健康保険まで付いてくる。これは、個人で全てを担うフリーランスとは大きく異なる、手厚いセーフティネットです。
そして、その中で僕が見つけたのが、「窓際FIRE」という新しい働き方の概念でした。
「辞めたいわけじゃない。でも、辞められるようにしておきたい」
一般的なFIRE(早期リタイア)は、完全に労働から解放されることを目指しますが、僕が求めているのは少し違いました。「働かなくてもいいという“逃げ道”を、常に手元に持っておきたい」という感覚です。
育休中、僕は赤ちゃんとの穏やかな日常の中で、この「家庭の余白」を何よりも大切にしたいと感じました。この心地よい暮らしを維持するため、そして将来にわたって守り続けるために、経済的な「逃げ場」を作っておくことの重要性を強く認識したのです。地方移住で得られた「がんばらない自分」と「整った暮らし」の心地よさとも通じる感覚です。
会社に戻れば、再び様々な業務や人間関係の課題に直面することもあるでしょう。しかし、もし本当に辛くなった時に「じゃあ、ちょっと降りますね」と穏やかに言えるだけの経済的な準備ができているだけで、心の余裕はまるで違ってきます。これは、「何もかもを諦める」ことではなく、むしろ「自分の人生における本当に大切なもの(家族、時間、心のゆとり)を諦めずに済むように、キャリアへの過剰なコミットを手放す」という、僕にとっての賢明な選択なのです。
僕が目指すのは、華々しい「完全リタイア」ではありません。会社という大きなシステムにそっと「しがみつき」ながらも、経済的な基盤を築くことで、働くことへの「圧」を減らし、人生に「あそび」を持たせること。それは、もしかしたら、世間で語られるFIREよりも、より穏やかで、より持続可能な幸福な働き方なのかもしれません。


エピローグ:中庸の生き方で耕す、僕だけの人生
高校中退というレールを外れた経験は、僕に常に「備え」の重要性を教えてくれました。そして、その備えは、資格取得という「人的資本」の積み上げと、地道な「資産形成」という「金融資本」の確立へと繋がっていきました。
かつては漠然とした不安から始まった僕の旅は、今、「窓際FIRE」という新しい目標を見つけ、穏やかな航海へと変わっています。「動きたくないわけじゃない。でも、無理に動かなくてもいいかな」──この、ある種の「中庸」の感覚が、今の僕にとっての最高の安心材料です。
僕は今、会社という土台に寄り添いながら、その足元で、自分の暮らしと人生という名の畑を、焦らず、しかし着実に耕しています。この「中庸」の生き方こそが、僕にとっての真の自由であり、心の平穏。高校中退から始まった僕の物語は、これからも、自分だけの幸福の形を追い求めて続いていくでしょう。

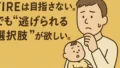
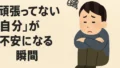
コメント