資産が5,000万円あっても、MacBook1台を買うのに1週間ぐらい迷ってしまう──これ、共感してくれる人いますか?
銀行口座の数字を見れば、買える。ローンも不要。
なのに「でも…本当に使うかな…?」「もっと安いのでもいいんじゃないか?」と、自分の中の“経済評論家”がスーツを着て会議を始めるんですよ。
おかしいですよね。高校生のとき、アルバイト代でゲーム機を買ったときは一切迷わなかったのに。
今じゃ同じ値段のカフェラテを頼むのすら「今日は家に豆あるしな…」ってなる。
なぜ、僕たちは「お金」を手にしても、自由に使えなくなるのだろうか。
今回は、僕自身の経験を振り返りながら、この不思議な心理と、お金の使い方から学んだ「幸せ」の定義についてお話ししたいと思います。
1. 心理的なポジションチェンジ──「攻め」から「守り」へ
なぜこうなるかというと、人間には「お金を減らす恐怖心」があるからです。
特に、僕のように一度心身を壊し、お金がないことの恐怖を味わった人は、それを減らすのが嫌になる。
だって、それが自分の安心感の源だから。
高校生の頃の僕
高校を中退し、バイト漬けの日々を送っていた頃の僕にとって、お金は「可能性を増やすもの」でした。バイト代で買ったゲーム機は、僕のひきこもり生活に光を与え、友人と繋がるきっかけを作ってくれた。それは、僕の人生の「攻め」の武器でした。
社会人になった僕
通信系大企業で働いていた頃も、お金は「守りの鎧」でした。激務とパワハラに苦しんでいた僕にとって、コツコツと貯めたお金は、「いつでもこの会社を辞められる」という心の支えだった。お金は、僕の安心感を守るための「守り」の道具に変わっていました。
若いころは「お金=可能性を増やすもの」だったのに、ある程度たまると「お金=安心感を守るもの」に変わる。
だから心理的には“攻め”から“守り”にポジションチェンジしてしまうのです。
2. 過去の自分との対話──大きな買い物は「未来の自分」まで関係する
それに加えて、大きな買い物って“未来の自分”の選択も背負うじゃないですか。
「このMacBook、3年後もちゃんと使ってるだろうか…」とか。
もはや自分が裁判員にでもなったかのように、過去の自分と未来の自分を天秤にかけ、慎重すぎる審議が始まる。
この心理は、僕が過去に衝動買いで失敗した経験から来ているのかもしれません。
昔、高価なブランド品や車を、見栄や一時的な欲求で買ったことがありました。しかし、それらはすぐに飽きてしまい、後悔だけが残りました。その経験から、僕は「本当に価値のある買い物」とは何かを深く考えるようになったのです。


3. 迷わず決めるための基準
では、どうすれば迷わずに、後悔しない買い物が出来るのだろうか?
僕の場合は、「欲しいかどうか」じゃなく、「使う場面が具体的に想像できるか」で判断します。
- ブログを書くとき、エルゴヒューマンに座って集中したい。→エルゴヒューマンは買う。
- リビングで家族と団らんするとき、ヘリノックスのチェアワンに座ってリラックスしたい。→チェアワンは買う。
- MacBookで、どのような作業を、どこで、どれくらいの頻度でするか、具体的に想像できる。→買う。
想像できたら買う。想像できないなら保留。
あとはレンタルやお試しを挟むと、「後悔するリスク」をかなり下げることができます。
それでも迷ったら、とりあえず“即決”じゃなく“即予約(仮)”。時間を置くと「やっぱり欲しい」と「どうでもいい」がハッキリします。
4. 守るだけじゃ、人生は薄味になる
結論、資産があっても迷うのは自然なこと。
むしろ「迷える」ということは、無駄遣いを防ぐフィルターがまだ働いてる証拠。
でも、守るばかりじゃ人生がちょっと薄味になる。
お金を減らさないことだけを考えていると、本当に価値ある経験やモノに出会う機会を逃してしまう。
お金を減らさないより、「お金を後悔なく使う」ほうが、長い目で見て幸せかもしれません。



おわりに:お金の使い方から、人生の満足度を考える
僕がたどり着いた結論は、お金の使い方は、その人の人生の満足度を映し出す鏡だということ。
ただ貯めるだけでは、安心は手に入っても、人生の豊かさは増えない。
お金を、自分の価値観に沿って、心から納得できる使い方をすること。
それが、僕が過去の失敗から学んだ、最も大切な教訓です。
そして、その基準で選んだMacBookは、僕の人生をより豊かにしてくれるでしょう。
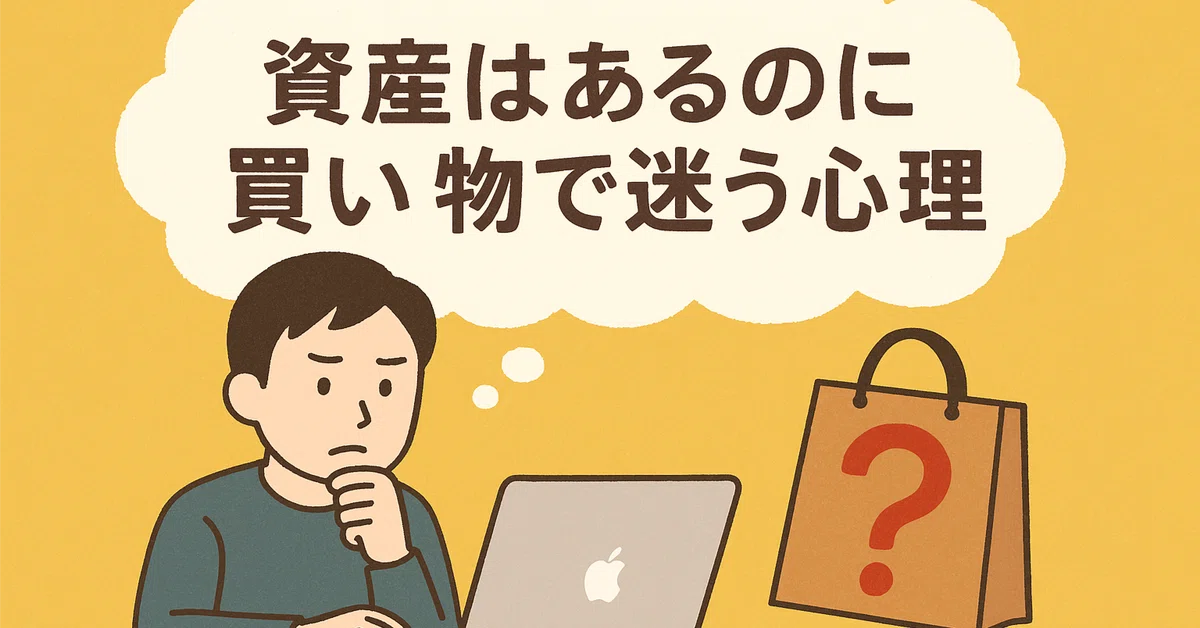
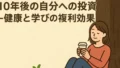
コメント